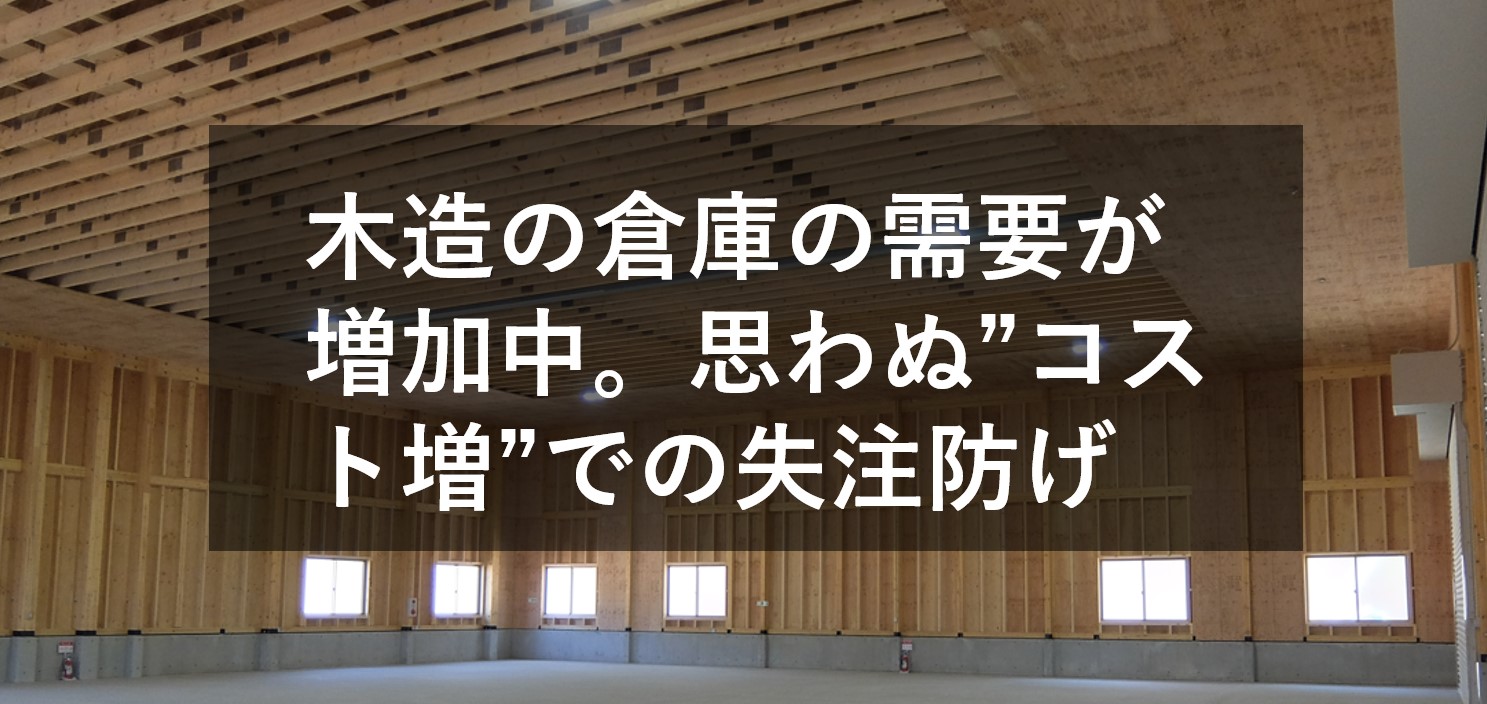
木造の倉庫に関するお問い合わせが増えています。
脱炭素社会への取り組みで、民間企業が自社施設を木造化する動きが活発化しているためです。
ただ、事業主の多くが、「今までの鉄骨造を単純に木造に置き換えよう」という発想で計画をしているため、コストを度外視して提案すると痛い目にあいます。
そうならないために、木造の倉庫を計画する時のポイントを押さえておきましょう。
先日もある工務店様から木造倉庫の相談を受けました。
鉄骨造から木造への置き換え案件だったため、問題の回避策をアドバイスしながら進めました。
依頼があった倉庫は9m×7mの一般的なものでした。
平面、立面、形状ともに普通の木造と大差はありません。
それほどコストがかからないという算段で計画を進めていましたが、倉庫のため階高が有効で5mほしいというオーダーでした。
この場合、もし5mの柱で計画すると構造計算をするまでもなく、120角の柱ではもたなくなります。
120角でもたない理由は材的な理由ではなく、細長比です。
木造の場合1/150の細長比が必要です(120角で5.2m、105角で4.6mまで)。
そうなると、どんなに強い集成材を使ったとしても、この項目を満足させることはできません。
130角、150角(130角で5.6m、150角で6.5mまで)という柱を使わざるを得ない状況になります。
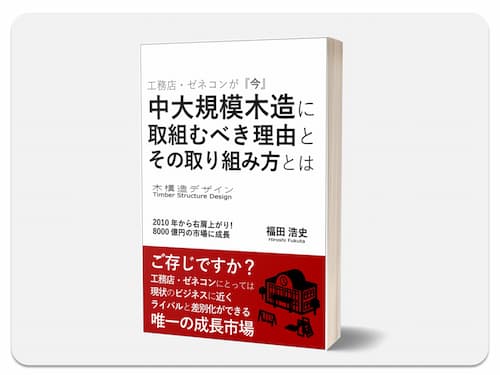
中大規模木造に取り組むべき理由とその取り組み方 この資料では、下記の内容を紹介しています。
|
倉庫の場合、スパンが飛ぶため外周の柱に相当な負担がかかります。
それに対しての軸力が必要なため、ぎりぎりの細長比では持たなくなる可能性もあります。
また、階高が4mを超えると耐風設計も考慮しなければなりません。
また、木造の場合、一般に流通している構造材が使えなくなった瞬間に、コストが数倍に膨れ上がります。
予算が合わない理由のほとんどがここにあります。
鉄骨造の置き換えで、簡単に木造で倉庫を作ろうと思っている事業者にとっては、想定外のシナリオです。
このような情報を事業者に告げずに、いきなり見積もりを提出すると、見積もりを見た瞬間に計画がストップしてしまいます。
そうならないために、回避策を事前に用意して、初期段階のプレゼンで伝えておかなければなりません。

【専門家解説】同じスパンで木造と鉄骨造を比べてみた
鉄骨造の計画をそのまま木造に置き換えると、どのようなことが起こるのか? 続きを読む
その際に木造のメリットも伝える必要があります。
一般的に言われている木造化のメリットは
1.木造は軽量で基礎にかかる負担を減らせる
2.流通量が多い住宅の資材を使用できるので、納期を短くできる
3.木造に適したプランが採用できれば、コストを抑えられるなどが挙げられます。
建物だけではなく基礎も含めたトータルの金額、そして、工期も含めた提案で、比較してもらうことが重要です。

木造の倉庫・店舗・事務所の坪単価&計画する時の3つのポイント
「倉庫は鉄骨が当たり前」「店舗、事務所も鉄骨でしょ」そんな常識は過去のものになりつつあります。続きを読む
ここでポイントになるのが階高です。
②の流通材の流用を視野に計画する必要があります。
もっとも一般的な解決策は、基礎高を上げるという方法です。
今回の倉庫も、基礎高を上げ、柱の高さを4mに抑えることで構造的な問題を回避しました。
例えば、階高が5m必要な場合は、基礎高を1.2m程にして柱を4m程度にします。柱の長さを短くすることで、細長比をクリアします。これによって120角で対応します。
ただ、基礎を高くすることに抵抗感がある事業主の方もいらっしゃいます。
そのため、丁寧な説明が必要です。
例えば、「倉庫の場合、室内をフォークリフトが走ることが多いです。フォークリフトが壁にぶつかることを考えると1.2mほど基礎を立ち上げたほうが安心できますが、いかがですか?」
と説明するのです。
このようにメンテナンスのことも考えた提案なら、事業者も容易に理解できます。
しかし、基礎高に関してはいくつか注意する点があります。
一つ目は、階高に対してRCの部分が半分を超えてしまうと、混構造扱いになるということ。そして、もう一つがコストです。
基礎が1.2mくらいまでなら、150巾、シングル配筋で問題になることはほぼないのですが、1.5mを超えてくると、ダブル配筋にして180巾にすることがあります。
そうなるとコストが変わってきます。
高基礎にすればすべてが解決できるという訳ではないので調整が必要です。
このような説明が事前に事業者にされていれば、メリットとして受け入れてもらえますが、見積もり時に、突然切り出されるとデメリットとして取られかねません。
今回は初期段階からアドバイスができたため、スムーズに進めることができました。
木造の倉庫はいくつかのポイントを押さえることでコストダウンが可能です。
倉庫の用途にもよりますが、内部に置かれる物の土圧、水圧、荷物圧なども考える必要がありますので、詳しくヒアリングして提案することが重要です。

福田 浩史
1999年三重大学大学院工学研究科・建築学専攻・修士課程修了、同年4月に熊谷組入社、構造設計部に配属。主に鉄筋コンクリート造や鉄骨造の高層マンション、店舗設計など大型建築物の構造設計を担当する。2002年6月エヌ・シー・エヌに移籍し、2020年6月取締役執行役員特建事業部長に就任。年間400棟以上の大規模木造の相談実績を持つ。2020年2月木構造デザインの代表取締役に就任。