
こんにちは。中大規模木造に特化した構造設計事務所木構造デザインの福田です。
500㎡以下の比較的小さな建物でも、中大規模木造は構造設計上の問題で悩むことが多くあります。
大空間や高さが求められるため、住宅の延長線上で進めてしまうとあとあと大きな問題になることもあります。
今回、もし、プレカット工場に構造上問題があると指摘された時の対応法を詳しく解説します。
「この図面では成立しません」と構造上の問題でプレカット工場から突き返されることがあります。
なぜなら、プレカット工場は「構造的に柱が何本必要ですよ」「梁成は〇〇㎜必要ですよ」というアドバイスをほぼしないからです。
そして、プレカット工場からの質問に対して「〇〇㎜の梁にすればもつので、〇〇㎜にしてください」と
構造的な答えを即答できる方はなかなかいません。
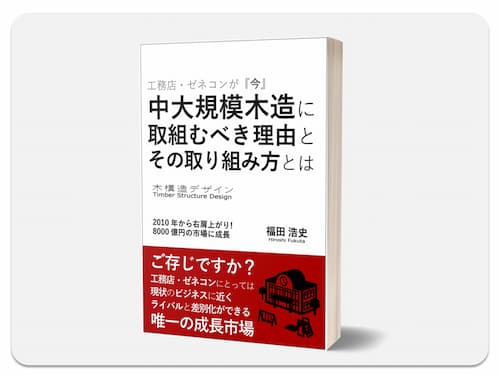
中大規模木造に取り組むべき理由とその取り組み方 この資料では、下記の内容を紹介しています。
|
実例で見ていきましょう。
ある工務店が、お付き合いのあるお客様から倉庫を建ててほしいという相談を受けました。
ヒアリングすると、それほど大きなものではなく形状もシンプルでした。
ただ、精米機を置くため高さが6m必要でした。
予算を考慮して木造を選択しプランを描いて提案すると、お客様の反応も上々。
しかし、見積もりのため図面をプレカット工場に送ると数日後「この図面では成立しません」という返答がきました。
CADによっては、プランを入力すると簡易的な壁量計算をしてくれます。
構造的に問題があるとCADが自動的にNGを出してくれます。
ただ、NGが出てしまうとプレカット工場は、そのまま進める訳にはいかないので依頼者に確認の連絡を入れることになります。
その時、構造的な解決策が大きな問題になります。
規模が小さいシンプルな倉庫は木造に向いています。
ただ、倉庫は高さを必要とすることが多く、5m、6mになることもざらです。
しかし、高さが4mを超えると構造的に柱のサイズが4寸でカバーできなくなります。
そうなると専門家の知見が必要になります。
中大規模木造に慣れている方なら、構造設計事務所に問い合わせをしCADで解析できない断面の裏付けを取ります。
しかし、相談ができる木造を熟知した構造設計者がいないと、計画がそこでストップしてしまうこともあります。
高さだけではなく、スパンや形状でも同じような問題が発生します。
住宅の場合、2間半を超えるスパンはほとんどありませんが、中大規模木造では当たり前のように超えてきます。
上記の倉庫もスパンが6mを超えるところもありました。
そうなると、CADのスパン表にないため梁成が決められず、プレカット工場から解決策を求められます。
こうなると、構造設計者への確認が必要になります。
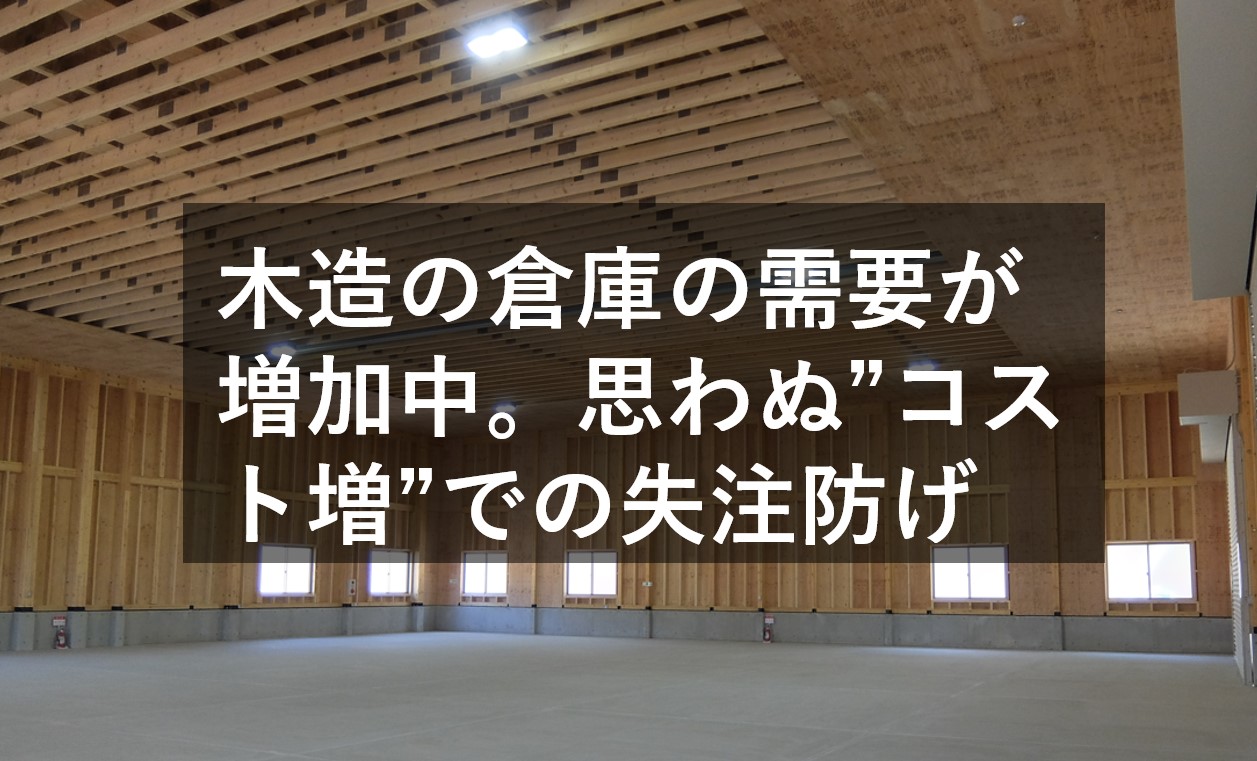
木造の倉庫の需要が増加中。思わぬコスト増での失注防げ
「今の鉄骨造を単純に木造に置き換えよう」と、コストを度外視して計画すると痛い目にあいます。続きを読む
住宅は4号特例で500㎡まで構造計算の省略が可能です。
しかし、特殊建築物の場合は200㎡を超えると確認申請時に何かしらの図面の添付が求められます。
その時に構造図も添付するので根拠が必要になります。
壁量計算でカバーできる範囲内なら、住宅の延長線上で進めることができるのですがそうでないと、どうしても専門家の知見が必要になります。
とはいえ、構造設計事務所に相談すると費用が発生するため、まだ契約ができるかわからない案件では相談ができず、計画がストップしてしまうこともあります。
弊社は、このようなつまずきをなくすために提携しているプレカット工場と一緒に、構造の相談を無料で行っています。
ただ、エラーが出たプランをプレカット工場から相談されるたびに「もっと早く構造設計者に相談をすればいいのに」と、思うことがあります。
本来ならば、計画の初期段階で構造のチェックを入れるべきです。
スケッチ段階で構造のチェックを入れればコストのかからない一般流通材で収まるプランにすることも可能です。
しかし、現実は違います。
プランの確定後、それもプレカット工場でエラーが出た後に、相談がきます。
それでは大きな材を入れて構造計算で帳尻を合わせるしかなくムリ、ムラのある構造になってしまいます。
中大規模木造に取り組む際はハードルが低い1000㎡未満のものだと比較的スムーズにはじめられます。
特に、意匠にこだわりの少ない倉庫は狙い目です。
一度経験してしまえば、木造の勘所が理解できます。
あとは、都度、初期段階で構造のチェックを入れて、コストや技術的な調整をすれば、大きな問題はほぼ起こりません。
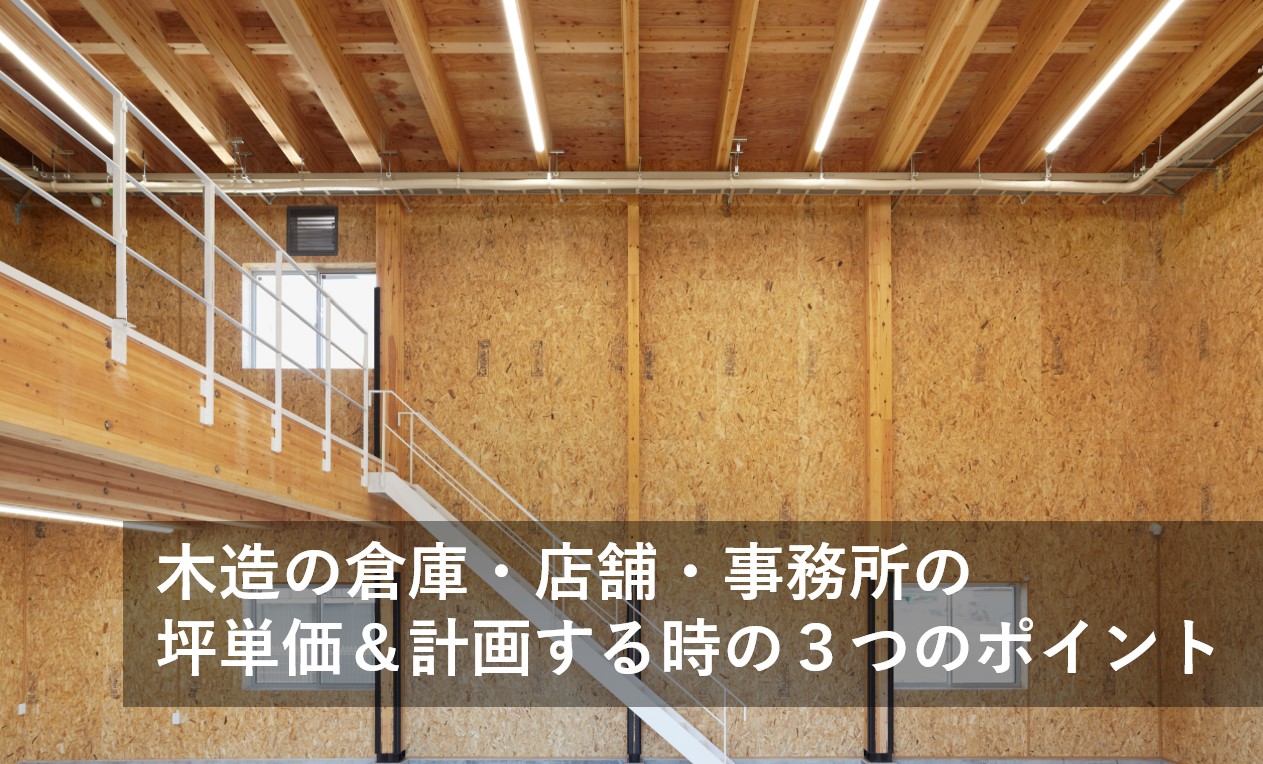
木造の倉庫・店舗・事務所の坪単価&計画する時の3つのポイント
「倉庫は鉄骨が当たり前」「店舗、事務所も鉄骨でしょ」そんな常識は過去のものになりつつあります。続きを読む
中大規模は、木造に精通した専門家の協力が必要不可欠です。
ただ、数字だけ計算して帳尻を合わせるような構造設計者では木材の調達やコストコントロールもままなりません。
木造に精通したパートナーと協力体制を築くことが重要なポイントになります。

福田 浩史
1999年三重大学大学院工学研究科・建築学専攻・修士課程修了、同年4月に熊谷組入社、構造設計部に配属。主に鉄筋コンクリート造や鉄骨造の高層マンション、店舗設計など大型建築物の構造設計を担当する。2002年6月エヌ・シー・エヌに移籍し、2020年6月取締役執行役員特建事業部長に就任。年間400棟以上の大規模木造の相談実績を持つ。2020年2月木構造デザインの代表取締役に就任。